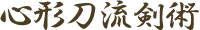心形刀流とは
心形刀流、名の由来
心形刀流と言う名の由来は「心の修養を第一義とし、技の練磨を第二とする。即ち技は形であり、心によって使うものである。心正しければ技正しく、心の修養足らざは技乱れる、そして、この技が刀の上に具現されるもので、流名に示すごとく心形刀流となる。」という考え方から来ています。
常に質実剛健で、伊庭道場は荒稽古で有名でした。
心形刀流組武芸形
現在、亀山に伝えられている技は、座った体制から青手の攻撃に大刀で応じる「抜合(居合)」表六本・裏六本、大刀の攻撃に対して大刀で応じる組太刀「大太刀之形」六本、小刀で応じる「小太刀之形」六本、大刀の攻撃に対して二振りの刀で応じる「二刀之形」といった剣術技や、「坐突・柄捕り(居合奥伝形)」と言う柔術技の他、「枕刀」と言われる槍・薙刀状の武具を用いた形が伝えられています。
「抜合(居合)」表六本

- 向覃中刀 (むたんちゅうとう)
- 逆膝覃中刀 (そうしつたんちゅうとう)
- 左小肘刀 (ひだりこひじとう)
- 右小肘刀 (みぎこひじとう)
- 後腰車刀 (ごこししゃとう)
- 一句貫刀 (いっくかんとう)
「抜合(居合)」裏六本

- 前肩井刀 (ぜんけんいとう)
- 透肩井刀 (とうけんいとう)
- 左撞留刀 (さしゅりゅうとう
- 右逆車刀 (みぎぎゃくしゃとう)
- 後肩留刀 (ごけんりゅうとう)
- 燕帰刀 (えんきとう)
組太刀「大太刀之形」六本

- 第一本目
華車刀(かしゃとう)・中合刀(ちゅうごうとう)・中道剣(ちゅうどうけん)・陰合刀(いんごうとう)・錺捨刀(ぼうしゃとう) - 第二本目
合捨刀(ごうしゃとう)・捨輪刀(しゃりんとう) - 第三本目
直和刀(ちょくわとう) - 第四本目
獅子乱刀(ししらんとう)・虎尾剣(こびけん)・陰捨刀(いんしゃとう) - 第五本目
陽知刀(ようちとう)・捲撃刀(けんげきとう)・陽見刀(ようみとう) - 第六本目
陽遊剣(ようゆうけん)・別車刀(べっしゃとう)
組太刀「小太刀之形」六本

- 中住別剣(ちゅうずみべっけん)
- 清眼左足(せいがんさそく)
- 清眼右足(せいがんうそく)
- 両手切(りょうてぎり)
- 裏之波(うらのなみ)
- 清明(眼)剣(せいがんけん)
「二刀之形」

- 向満子(むこうまんじ)
- 横満子(よこまんじ)
- 横満子残(よこまんじのこし)
- 刀合切(とうごうせつ)
- 相捲(そうまくり)
- 清眼破(せいがんやぶり)
- 柳雪刀(りゅうせつとう)
- 鷹の羽(たかのは)
- 水月刀(すいげつとう)
- 三心刀(さんしんとう)
- 無拍子(むびょうし)
「枕刀」
- 右押之甲手切(みぎおしのこてぎり)
- 左押之甲手切(ひだりおしのこてぎり)
- 脾尻突(ももしりつき)
- 右押甲手切(みぎおしこてぎり)
- 左押甲手切(ひだりおしこてぎり)
- 右脛切(みぎすねぎり)
- 両脛切(りょうすねぎり)

「坐突・柄捕り」
- 坐突(坐技) 三本
- 柄捕(立技) 三本
- 参考文献:「伊庭八郎のすべて」(新人物往来社編)